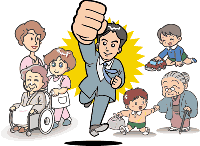今事業の目的は、NPOのマネージメント能力の向上と、各活動団体・活動者のネットワーク構築を促し、宮崎県内のNPO活動の活性化をはかることにあった。
NPOマネージメント講座受講生を募集する際、宮崎県が保有している県内のボランティア団体の名簿を参考とした。これによると、現在約300あまりの団体が様々な活動を行っている。他県との比較などを行っていないため、この数字の大小について述べることはできないが、我々が予測していたよりもかなり大きい数字であったと言える。これら約300の団体すべてに、案内書および申込書、受講生登録カード(資料参照)を郵送した。それ以外でも、宮崎市内でNPOやボランティア活動団体の会議等があった際に告知をおこない、参加を呼びかけた。その結果、第1回目の講座には 名の申込があった。その後新たな申込もあり、最終回講座までに参加申込者数は総計102名となった。
10月13日に開校式および第1回講座を行い、以降3月23・24日の最終回まで毎月1回、計6回の講座を行った。講座日程は、遠方からの参加者も多い点を考慮し、土・日を中心に設定した。各回講座の約3週間前までに、登録している受講生に講座日程や講師を紹介する文書および参加申込書を送り、出欠を把握するようにした。
各回の講座テーマは、NPOを運営していく上で必要な知識や理念に基づいて設定し、計14名の講師が各テーマに沿った講演を行った。各講師の活動分野は、福祉・環境・子育て支援・文化振興など様々であり、受講生もそれぞれの活動の参考となる話を聞けたことと思う。一方各講師が、それぞれの活動経験に基づきながらも、自分の分野の話に特化せず、NPOを総合的に語るという配慮もされたことで、どの回も「NPOマネージメント」という今講座の主題に沿った講演となった。また、実践的な知識を身につける目的で、KJ法を用いて議論を進めるワークショップ(第2回講座)・資金調達と税制についての分科会(第3回講座)・宮崎のマスコミ関係者によるマスコミ活用法についての講座(第5回講座)も行った。
各回の講座終了ごとに行ったアンケート(アンケート結果資料参照)では「次回講座に対する意見、要望」をたずねたが、これに対する解答は次回講座の講師に事前に伝え、講演内容の中にとり入れてもらうようにした。
受講生から提出された登録カードはファイルに綴じ、受講生が互いを知るきっかけとなるよう自由に閲覧できる形をとった。また第3回講座、第4回講座の終了後に、受講生間の交流を深めるために親睦会を行った。講座だけでは、時間の制約もあって受講生同氏が互いに語り合う機会はなかなか得られないが、この親睦会が、それぞれの活動を紹介したり情報を交換する良いチャンスとなったようである。また、これには講師にも参加していただいたので、受講生が直接講師と交流する貴重な時間となった。
第1回から第5回講座までは、講座日程は1日または半日で組んだが、最終回の第6回講座は、これまでの集大成として5人の講師を招き、2日間にわたって開催した。この回は公開講座の形をとり、これまでの受講生に加えて新たに22名の参加があった。講座1日目の夜には、名刺交換会を兼ねた親睦会を行った。これは、宮崎市で様々なイベントや交流活動を行っている団体「青年ネットワーク」と合同で開催した。講師5人にも出席いただき、総計63名が参加した。受講生も積極的に講師陣に話を聞きにいき、また受講生間、受講生と青年ネットワークメンバー間にも新たな交流が生まれ、大変盛況な会となった。
講座の全日程を終えた後、終了式をおこなった。6回の講座中、4回以上出席した受講生に終了証書を授与した。対象者は31名であった。最終回講座のアンケートでは、本講座全体を評価してもらうための質問を用意したが、全体的にかなり高い評価を得ることができた(第6回講座アンケート結果参照)。感想の欄にも、「大変勉強になった。」「いつ参加しても、来て良かったと思っている。」「もっと学びたいのでこれからも続けてほしい。」といった声があった。
今事業の目的の1つである「NPOのマネージメント能力向上」については、講座に参加し、受講生が各自の疑問を解いていく過程で達成されていったと思う。また、講師からNPOの理念的な部分や現実の部分を聞くことも、それを助けたのではないだろうか。今後は受講生が、今回得た知識を補強し、学んだことを実践にいかせるよう、アフターケアとなる動きが必要となるだろう。
もう1つの目的「各活動団体・活動者のネットワーク構築」については、今講座が他の団体・個人の存在を知るきっかけとなり、また3回の親睦会を通して互いの交流ははかられたが、具体的なネットワーク構築の域までには達しなかった。これまでの我県の活動団体・個人の様子を見ると、ネットワーク形成の目立った動きはなかった。しかし最終回で行ったアンケートの結果によると、ネットワークの必要性については解答した全員が必要であると答えている。その理由として、「皆で取り組む方がよりよい活動ができる」「情報を孤立化させないため」「県全体のレベルアップにつながる」などがあった。これまでも必要性を感じていながら、その機会が無かったとも言える。ネットワーク構築に必要なのは、NPOというものを分野わけせずに総合的にとらえ、様々な活動から学びあって協力しあうという姿勢である。最も理想的なのは、この講座で出会った受講生同士が今後も情報を交換し、つながりを継続させながら活動協力が始まることであるが、時間や距離の問題もあり、現実には難しい面も多い。しかし全体報告で述べた様に、県内には約300にのぼる活動団体がある。人々のため、地域のため、何か役に立ちたいという思いをもつ人達が、それだけいるということである。その思いをつなぎあわせ、協力していけば、これまでにはなかった大きな力をつくりだすことができるだろう。今回の講座は、ネットワークの大切さを再認識する機会であったと同時に、力を生み出す最初の一歩となった。ネットワーク形成については、我々も今後の大切な事業の1つとして位置付けている。他県の事例も参考にし、当団体がコーディネーターとして各団体・個人の連絡役を担うことも視野に入れながら、これから具体案を提示していきたい。
また、アンケートでも講座の内容自体は充実したものと一定の評価を得てはいるが、企画当初、各回の講座を50名規模、最終回のシンポジウムは200名規模で計画していたが、その数までに至らなかったのが反省の材料といえる。これだけの内容を盛り込んだ講座であったが、一部の熱心な人しか継続して参加しない状況を分析する必要がある。
県内各地から集ることを想定し、土日、祭日にスケジューリングしたのだが、それが正しい選択であったかどうかは充分な検証が必要である。市民活動、ボランティアの人達の、自分達の本来の活動の時間やイベントと重なってしまい欠席する、というパターンもしばしば見受けられた。新聞各社や各マスコミにも取上げられてはいたが、契約から1回目の講座まで時間が限られていたこともあり、十分な告知展開ができなかったこともある。次回このような企画を行う際には、動員にも細心の注意をはらい臨みたい。